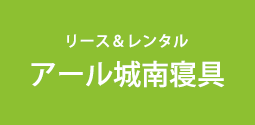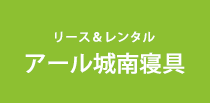冬布団に要注意!!
こんにちは!東京都・横浜市・川崎市の布団レンタルのアール城南寝具です♪
今日は朝から穏やかな天気でとても過ごしやすい日でしたね。
ただ、やはり朝晩はもうすっかり冷え込んできて寒いですよね。
慌てて冬用の掛け布団を出した方も多いのではないでしょうか?
ただ、急に出した布団を使ったら翌朝くしゃみや咳、目がかゆいなどの症状がでていませんか?
今回そんな「要注意」の布団に関しての記事がありましたのでご紹介します。
(以下、文春オンライン引用)
毎日つかう布団。でも布団のケア方法を改めて学ぶ機会を持たないまま、自己流に扱っているようなケースも多いのではないでしょうか。
“要注意”の布団の状態とは?
いささか不安がある方は、一度ご自身の布団の状態をチェックしてみましょう。とりわけ、要注意な布団の条件は以下のようなものになります。
・半年以上フローリングの床に敷きっぱなしの布団
汗や結露によって床と敷布団の間に、カビが広域に生えている可能性があります。黒ずみの有無、シミに注意。
・半年以上、2段ベッドの上段に敷きっぱなしになっている布団
風通しがいいと認識されやすい2段ベッド上部の布団。カビ率が意外に高いためよく見てみましょう。
・1年以上何もケアしていないベッドの上の万年床風布団
ベッド本体、ベッド下(引き出し等の中身)含めてカビが生えているケースがあります。
・発熱など体調不良時を経た布団
回復後、そのまま使い続けている場合、汗や体液によるカビやシミが生じてしまうことがあります。
・ソファ代わりにしてお菓子を食べたり、食事をしたりしている布団
こぼれた食べ物をエサにして、ダニが繁殖しやすい状況になっています。
・同じ空間で洗濯物の部屋干しを日常的に行っている布団
洗濯物の水分を布団が吸っている可能性があり、カビ、ダニリスク共に高い状態です。
・加湿器を年中つけている部屋の布団
過剰に加湿を行っている部屋の布団も湿気によるカビ、ダニリスクが。換気頻度の少ない部屋の場合も同様です。
シミや黒ずみはカビ、チクチクするホコリはダニ、ニオイが強い場合はバクテリアが繁殖している可能性があります。
もしひとつでも思い当たる項目があれば注意! 今回はこういった布団の、「ケアの基礎の基礎」をお伝えしたいと思います。
まず、和布団・ベッドを問わず、寝具ケアの基本は、以下の2つです。
1、表面、内部共に「乾燥させる」
2、表面の「汚れを除去する」
私たちが毎日寝る度に、布団は“汚れている”ということをまず意識してください。汗などの湿気、皮脂などの分泌物、空気中や床(畳など)から吸収するホコリなどが主なこの汚れの原因になります。
おねしょや嘔吐といった派手な出来事がない限りは、汚れのペース自体は緩やかです。けれども毎日蓄積される湿気や汚れにプラスして、就寝にともなう体温(温度)によって少しずつバクテリア(細菌)が繁殖して臭いが出たり、カビが生えて徐々に黒ずんでいったり、ダニがわくことで粉っぽいホコリ(内容はダニの死体の欠片や糞)が増えたりしていきます。
こういった典型的な布団の汚れが、健康に急激な影響を及ぼすことは稀です。ただアレルギー性疾患、皮膚炎、鼻炎、喘息といった症状がじわじわ出て初めて、汚れの存在に思い当たることになりがちなのです。
これらの害を予防するためには、布団から身体由来の湿気を飛ばすこと、つねに乾燥を促すことが大切です。
布団を「干す」方法は色々ある
布団を乾燥させる方法ですが、必ずしもベランダなどの「屋外に干す」一択ではありません。
「干す」にしても、
・椅子などにかぶせて、エアサーキュレーターなどで風を送る「部屋干し」
これは、なるべく広い面積を空気にさらすことで湿気を飛ばします。
・浴室乾燥機などを使う「屋内干し」
浴室掃除を済ませて水分を拭った浴室で、自立する敷き布団などを乾かします。浴室乾燥機は温度が高くなり、タイマーもあるので少し布団の湿気の多いケースに向いています。
など、いわゆる洗濯物の「部屋干し」の応用が利くので柔軟にくふうしてみてください。
・布団の入る「コインランドリーの乾燥機」利用
自家用車のある場合は比較的簡単に持っていけるコインランドリーの活用も乾燥の一手段です。ちなみにクルマのない筆者は布団を90リットルサイズのゴミ袋に詰め込み担いで徒歩で持参します。意外と持ち運びやすいです。ご参考まで。
・電気式の布団乾燥機を利用する方法
近年の布団乾燥機は布団の下にマットを敷き込むのではなく、温風の出るホースを布団と布団の間に差し込むだけ、と手間が大変少なく簡単になっています。
なども大変有効であるなど、「乾燥させる」方法は実は多岐に渡り、布団の下に除湿マットを敷き込む、電気毛布やホットカーペットなどの上に敷いて温めるといった隠し球もあります。ただ、くれぐれも「乾燥させながら寝る」といった行為は、低温やけどなどの危険があるので試さないようにしてください。
カバー類の洗濯の頻度
そして2つ目のポイントとなる「汚れの除去」。これはシーツ、カバー類を使用することで布団本体の汚れを減らし、布部分の衛生状態を高める方法と、布団クリーナー(布団掃除機)を利用する方法、布団を丸洗いする方法があります。
布団に付着するフケ、抜け毛、ホコリ等の「乾いた汚れ」は布団クリーナーで除去できます。これは毎日行えればそれに越したことはありませんが、汚れが気になる都度、抜け毛等の具合にもよりますが週に1回ほど行えれば及第でしょう。
ただ皮脂や汗といった分泌物による「湿った汚れ」は洗濯で落とすことが必要になってきます。この分泌物量は個人差が大きく、家族間でも全く汚れ方が異なるので必要な頻度は一概に言えません。ただ発汗量の多い人や子どもの場合カバー類は1、2週間に1度程度を目安に洗濯できるといいのではないかと思います。
ここで大切な点は、インテリア視点でのカバーリング等と衛生的な意味での洗濯のしやすさはあまり両立しない、ということです。暮らしにかけられる手間と優先順位によって、自分はどのような方法を採れるのか、ぜひ考えてみてください。
これは一例なのですが、ある育ち盛りの年齢の子どもがいるお宅では、逆にカバー類一切なしで、全て家庭かコインランドリーでの丸洗い洗濯が可能な布団本体を使用しています。子どもがおねしょをすれば、どうせ布団の中まで染みてしまうので、カバーを外したりかけたりする手間の方がかかるという判断です。
また布団でも敷き布団の多くや、ベッドマットレスの場合、奥底まで汚れた後の自力でのケアが「できない」場合もあります。専門業者への外注をしなければならないということです。
臭いやカビなどが取れなくなり、大きな布団やマットレスそのものの買い替えを余儀なくされるケースも少なくありません。これから寝具全般を購入する際にはぜひ“手入れのしやすさ”も考慮してみてください。
布団ケアの盲点とは?
さて布団ケアというと主に敷き布団、掛け布団の2点に目が行きがちですが、実は布団よりも汚れやすい、「危ない」存在があります。「枕」です。
汚れやすく汗ばみ蒸れやすい頭を毎日乗せており、かつ私たちは無意識によだれを垂らして寝ていると思われます。それらを受け止めるのが「枕」です。長期間愛用した枕の生地があやしい色や謎の模様を呈していることに気づいたことのある人も少なくないのではないでしょうか。
ただ、この枕の扱いには現実的に難しいものがあります。というのは市販の枕には素材の理由で丸洗いできないものがたいへん多いからです。しかしバクテリア、カビ、ダニなどによる健康リスクは、顔に近い分だけ布団の比ではありません。
ワンシーズンに一度は洗濯を
枕は寝心地だけでなく、その製品のケア方法までしっかり把握したうえで購入したいものです。家庭の洗濯機で洗える枕であるならば、できるだけ頻繁に、たとえば最低でもワンシーズンに1回は洗うようにしましょう。洗えない枕の場合はシーツ同様かもう少し頻繁にカバーを交換・洗濯し、布団よりも念入りに日々の乾燥を心がける必要があるでしょう。
基本的にあらゆる暮らし周りのものごとは他人に見せる(見える)ものではありませんが、そのなかでもとりわけ寝室、寝具周りの取り扱いは各家、各人「ブラックボックス」になりがちです。そのため、漠然と負担・不快を感じていながらそのままにしているようなケースが少なくないようです。
眠りは健康の礎、その場である寝室、寝具の重要性はとても高いはずです。暮らし全体に過剰な負担をかけず、しかし快適な睡眠を妨げないさじ加減でのケアを、各々模索していっていただければと思います。
弊社ではふとん丸洗いサービスも行っておりますので、いつでもご連絡いただければ対応させていただきます。
今日は朝から穏やかな天気でとても過ごしやすい日でしたね。
ただ、やはり朝晩はもうすっかり冷え込んできて寒いですよね。
慌てて冬用の掛け布団を出した方も多いのではないでしょうか?
ただ、急に出した布団を使ったら翌朝くしゃみや咳、目がかゆいなどの症状がでていませんか?
今回そんな「要注意」の布団に関しての記事がありましたのでご紹介します。
(以下、文春オンライン引用)
毎日つかう布団。でも布団のケア方法を改めて学ぶ機会を持たないまま、自己流に扱っているようなケースも多いのではないでしょうか。
“要注意”の布団の状態とは?
いささか不安がある方は、一度ご自身の布団の状態をチェックしてみましょう。とりわけ、要注意な布団の条件は以下のようなものになります。
・半年以上フローリングの床に敷きっぱなしの布団
汗や結露によって床と敷布団の間に、カビが広域に生えている可能性があります。黒ずみの有無、シミに注意。
・半年以上、2段ベッドの上段に敷きっぱなしになっている布団
風通しがいいと認識されやすい2段ベッド上部の布団。カビ率が意外に高いためよく見てみましょう。
・1年以上何もケアしていないベッドの上の万年床風布団
ベッド本体、ベッド下(引き出し等の中身)含めてカビが生えているケースがあります。
・発熱など体調不良時を経た布団
回復後、そのまま使い続けている場合、汗や体液によるカビやシミが生じてしまうことがあります。
・ソファ代わりにしてお菓子を食べたり、食事をしたりしている布団
こぼれた食べ物をエサにして、ダニが繁殖しやすい状況になっています。
・同じ空間で洗濯物の部屋干しを日常的に行っている布団
洗濯物の水分を布団が吸っている可能性があり、カビ、ダニリスク共に高い状態です。
・加湿器を年中つけている部屋の布団
過剰に加湿を行っている部屋の布団も湿気によるカビ、ダニリスクが。換気頻度の少ない部屋の場合も同様です。
シミや黒ずみはカビ、チクチクするホコリはダニ、ニオイが強い場合はバクテリアが繁殖している可能性があります。
もしひとつでも思い当たる項目があれば注意! 今回はこういった布団の、「ケアの基礎の基礎」をお伝えしたいと思います。
まず、和布団・ベッドを問わず、寝具ケアの基本は、以下の2つです。
1、表面、内部共に「乾燥させる」
2、表面の「汚れを除去する」
私たちが毎日寝る度に、布団は“汚れている”ということをまず意識してください。汗などの湿気、皮脂などの分泌物、空気中や床(畳など)から吸収するホコリなどが主なこの汚れの原因になります。
おねしょや嘔吐といった派手な出来事がない限りは、汚れのペース自体は緩やかです。けれども毎日蓄積される湿気や汚れにプラスして、就寝にともなう体温(温度)によって少しずつバクテリア(細菌)が繁殖して臭いが出たり、カビが生えて徐々に黒ずんでいったり、ダニがわくことで粉っぽいホコリ(内容はダニの死体の欠片や糞)が増えたりしていきます。
こういった典型的な布団の汚れが、健康に急激な影響を及ぼすことは稀です。ただアレルギー性疾患、皮膚炎、鼻炎、喘息といった症状がじわじわ出て初めて、汚れの存在に思い当たることになりがちなのです。
これらの害を予防するためには、布団から身体由来の湿気を飛ばすこと、つねに乾燥を促すことが大切です。
布団を「干す」方法は色々ある
布団を乾燥させる方法ですが、必ずしもベランダなどの「屋外に干す」一択ではありません。
「干す」にしても、
・椅子などにかぶせて、エアサーキュレーターなどで風を送る「部屋干し」
これは、なるべく広い面積を空気にさらすことで湿気を飛ばします。
・浴室乾燥機などを使う「屋内干し」
浴室掃除を済ませて水分を拭った浴室で、自立する敷き布団などを乾かします。浴室乾燥機は温度が高くなり、タイマーもあるので少し布団の湿気の多いケースに向いています。
など、いわゆる洗濯物の「部屋干し」の応用が利くので柔軟にくふうしてみてください。
・布団の入る「コインランドリーの乾燥機」利用
自家用車のある場合は比較的簡単に持っていけるコインランドリーの活用も乾燥の一手段です。ちなみにクルマのない筆者は布団を90リットルサイズのゴミ袋に詰め込み担いで徒歩で持参します。意外と持ち運びやすいです。ご参考まで。
・電気式の布団乾燥機を利用する方法
近年の布団乾燥機は布団の下にマットを敷き込むのではなく、温風の出るホースを布団と布団の間に差し込むだけ、と手間が大変少なく簡単になっています。
なども大変有効であるなど、「乾燥させる」方法は実は多岐に渡り、布団の下に除湿マットを敷き込む、電気毛布やホットカーペットなどの上に敷いて温めるといった隠し球もあります。ただ、くれぐれも「乾燥させながら寝る」といった行為は、低温やけどなどの危険があるので試さないようにしてください。
カバー類の洗濯の頻度
そして2つ目のポイントとなる「汚れの除去」。これはシーツ、カバー類を使用することで布団本体の汚れを減らし、布部分の衛生状態を高める方法と、布団クリーナー(布団掃除機)を利用する方法、布団を丸洗いする方法があります。
布団に付着するフケ、抜け毛、ホコリ等の「乾いた汚れ」は布団クリーナーで除去できます。これは毎日行えればそれに越したことはありませんが、汚れが気になる都度、抜け毛等の具合にもよりますが週に1回ほど行えれば及第でしょう。
ただ皮脂や汗といった分泌物による「湿った汚れ」は洗濯で落とすことが必要になってきます。この分泌物量は個人差が大きく、家族間でも全く汚れ方が異なるので必要な頻度は一概に言えません。ただ発汗量の多い人や子どもの場合カバー類は1、2週間に1度程度を目安に洗濯できるといいのではないかと思います。
ここで大切な点は、インテリア視点でのカバーリング等と衛生的な意味での洗濯のしやすさはあまり両立しない、ということです。暮らしにかけられる手間と優先順位によって、自分はどのような方法を採れるのか、ぜひ考えてみてください。
これは一例なのですが、ある育ち盛りの年齢の子どもがいるお宅では、逆にカバー類一切なしで、全て家庭かコインランドリーでの丸洗い洗濯が可能な布団本体を使用しています。子どもがおねしょをすれば、どうせ布団の中まで染みてしまうので、カバーを外したりかけたりする手間の方がかかるという判断です。
また布団でも敷き布団の多くや、ベッドマットレスの場合、奥底まで汚れた後の自力でのケアが「できない」場合もあります。専門業者への外注をしなければならないということです。
臭いやカビなどが取れなくなり、大きな布団やマットレスそのものの買い替えを余儀なくされるケースも少なくありません。これから寝具全般を購入する際にはぜひ“手入れのしやすさ”も考慮してみてください。
布団ケアの盲点とは?
さて布団ケアというと主に敷き布団、掛け布団の2点に目が行きがちですが、実は布団よりも汚れやすい、「危ない」存在があります。「枕」です。
汚れやすく汗ばみ蒸れやすい頭を毎日乗せており、かつ私たちは無意識によだれを垂らして寝ていると思われます。それらを受け止めるのが「枕」です。長期間愛用した枕の生地があやしい色や謎の模様を呈していることに気づいたことのある人も少なくないのではないでしょうか。
ただ、この枕の扱いには現実的に難しいものがあります。というのは市販の枕には素材の理由で丸洗いできないものがたいへん多いからです。しかしバクテリア、カビ、ダニなどによる健康リスクは、顔に近い分だけ布団の比ではありません。
ワンシーズンに一度は洗濯を
枕は寝心地だけでなく、その製品のケア方法までしっかり把握したうえで購入したいものです。家庭の洗濯機で洗える枕であるならば、できるだけ頻繁に、たとえば最低でもワンシーズンに1回は洗うようにしましょう。洗えない枕の場合はシーツ同様かもう少し頻繁にカバーを交換・洗濯し、布団よりも念入りに日々の乾燥を心がける必要があるでしょう。
基本的にあらゆる暮らし周りのものごとは他人に見せる(見える)ものではありませんが、そのなかでもとりわけ寝室、寝具周りの取り扱いは各家、各人「ブラックボックス」になりがちです。そのため、漠然と負担・不快を感じていながらそのままにしているようなケースが少なくないようです。
眠りは健康の礎、その場である寝室、寝具の重要性はとても高いはずです。暮らし全体に過剰な負担をかけず、しかし快適な睡眠を妨げないさじ加減でのケアを、各々模索していっていただければと思います。
弊社ではふとん丸洗いサービスも行っておりますので、いつでもご連絡いただければ対応させていただきます。
睡眠や寝具のレンタル・丸洗いなどでお悩みの際はアール城南寝具へご相談下さい!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
東京の布団レンタルのプロ「アール城南寝具」
●東京本社
東京都品川区旗の台3-7-10
TEL:03-3781-4547
FAX:03-3781-8887
電話受付時間 9:00~21:00
お問合せはこちらから>>>>>
横浜・川崎の布団レンタルのプロ「アール城南寝具」
●横浜支店
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東4-7-18
TEL:045-941-7065
FAX:045-941-7087
電話受付時間 9:00~21:00
お問合せはこちらから>>>>>◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
東京の布団レンタルのプロ「アール城南寝具」
●東京本社
東京都品川区旗の台3-7-10
TEL:03-3781-4547
FAX:03-3781-8887
電話受付時間 9:00~21:00
お問合せはこちらから>>>>>
横浜・川崎の布団レンタルのプロ「アール城南寝具」
●横浜支店
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東4-7-18
TEL:045-941-7065
FAX:045-941-7087
電話受付時間 9:00~21:00
お問合せはこちらから>>>>>◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇