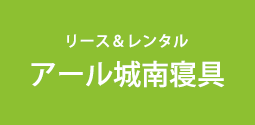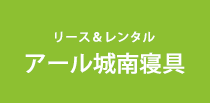2月3日は「不眠の日」 あなたは大丈夫!?
みなさんこんにちは!アール城南寝具です!
1月も今日で終わりですね。
2025年になって早くも1ヶ月が過ぎようとしていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
さて、もうすぐ2月3日は「不眠の日」です。
みなさんは普段ぐっすり眠れていますか。

「不眠の日」とは?
日本人の半数以上はなんらかの不眠症状を抱えていると言われています。しかし、その多くの人が改善方法などの正しい知識を持っていないことから、適切な情報発信を行うことを目的として、睡眠改善薬「ドリエル」などを製造・販売するエスエス製薬株式会社が制定しました。
日付は2と3で「不眠」と読む語呂合わせから2月3日になりました。
また不眠の症状は一年中起こるものなので、毎月23日も2と3で「不眠の日」となっています。
日付は2と3で「不眠」と読む語呂合わせから2月3日になりました。
また不眠の症状は一年中起こるものなので、毎月23日も2と3で「不眠の日」となっています。
主な不眠(睡眠障害)のタイプ
不眠症にはさまざまな症状がありますが、主に以下の4つのタイプに分けられます。
入眠困難タイプ
布団に入ってから寝つくまでに時間がかかる。
寝ようと思ってもすぐ寝られず、眠れるまでに1時間以上かかり、それを苦痛と感じる状態です。
睡眠障害でよく見られる症状で、不安や緊張が強い時に発症しやすいです。
寝ようと思ってもすぐ寝られず、眠れるまでに1時間以上かかり、それを苦痛と感じる状態です。
睡眠障害でよく見られる症状で、不安や緊張が強い時に発症しやすいです。
中途覚醒タイプ(睡眠維持障害)
夜中に何度も目が覚めたり、一度目が覚めるとその後なかなか寝つけない。
目が覚める時間や回数は個人差があり、日本の成人で最も訴えが多い不眠のタイプです。
目が覚める時間や回数は個人差があり、日本の成人で最も訴えが多い不眠のタイプです。
早朝覚醒タイプ
起きたい時間より2時間以上早く目が覚め、まだ眠りたいのに、眠れなくなってしまう。
高齢者に多い不眠のタイプで、歳を重ねると体内時計が崩れやすくなることで、若者より夜遅くまで起きられなくなり早寝早起きになります。
また、うつ病にもよく見られる症状です。
高齢者に多い不眠のタイプで、歳を重ねると体内時計が崩れやすくなることで、若者より夜遅くまで起きられなくなり早寝早起きになります。
また、うつ病にもよく見られる症状です。
熟眠障害タイプ
睡眠時間は足りているはずなのに、熟睡感が得られない。
眠りの要素には「時間」と「質」の2つがあり、本当に重要なのは「時間」よりも「質」だと言われています。
十分に質の良い睡眠が取れたときには短時間でも疲れが回復し、反対に質の低下した眠りは何時間眠っても疲れが取れず、逆に体がしんどくなってしまうことがあります。
睡眠の質が低下する原因として、就寝中に呼吸が止まり睡眠の質が悪くなる「睡眠時無呼吸症候群」や、就寝中に足がぴくんぴくんとした動きを繰り返して眠りが浅くなる「周期性四肢運動障害」などの病気が関係していることもあります。
どちらの睡眠障害も本人は気付きにくいので注意が必要です。他の種類の睡眠障害と合併していることもあります。
眠りの要素には「時間」と「質」の2つがあり、本当に重要なのは「時間」よりも「質」だと言われています。
十分に質の良い睡眠が取れたときには短時間でも疲れが回復し、反対に質の低下した眠りは何時間眠っても疲れが取れず、逆に体がしんどくなってしまうことがあります。
睡眠の質が低下する原因として、就寝中に呼吸が止まり睡眠の質が悪くなる「睡眠時無呼吸症候群」や、就寝中に足がぴくんぴくんとした動きを繰り返して眠りが浅くなる「周期性四肢運動障害」などの病気が関係していることもあります。
どちらの睡眠障害も本人は気付きにくいので注意が必要です。他の種類の睡眠障害と合併していることもあります。
このような症状が1ヶ月以上続き、倦怠感・意欲低下・集中力低下など、日中に様々な不調が現れたり日常生活への支障などが見られるようになると、「不眠症」と診断される可能性が高いと言えます。
不眠症の原因とは?
不眠症は、心身的な要因や環境によるものなど、さまざまな原因があります。
睡眠リズムの乱れ
不規則な生活習慣や不適切な睡眠環境などが原因で睡眠リズムが乱れ、不眠が生じるケースです。
例えば、夜間勤務などにより睡眠時間が不規則であったり、寝具が体に合っていない、温度・湿度・明るさなど睡眠環境が整っていない場合も睡眠リズムが乱れやすくなります。
例えば、夜間勤務などにより睡眠時間が不規則であったり、寝具が体に合っていない、温度・湿度・明るさなど睡眠環境が整っていない場合も睡眠リズムが乱れやすくなります。
心理的なストレスに関連した不眠
不安や心配事などからくる心理的なストレスや緊張が原因で、不眠の症状が表れるケースです。
例えば、仕事のトラブルや重要なプレゼンがあるなどの緊張感や対人関係の悩み、親しい人の死などで眠れなくなるのは、不眠に繋がる心理的な要因があるからです。特に几帳面で真面目な性格の人はストレスを強く感じやすく、不眠症になるリスクが高いと言われています。
例えば、仕事のトラブルや重要なプレゼンがあるなどの緊張感や対人関係の悩み、親しい人の死などで眠れなくなるのは、不眠に繋がる心理的な要因があるからです。特に几帳面で真面目な性格の人はストレスを強く感じやすく、不眠症になるリスクが高いと言われています。
心の病気に関連した不眠
うつ病・不安障害・パニック障害・心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患により、不眠や過眠(眠気)の症状があらわれることがあります。
うつ病患者の約80%~85%に不眠が認められ、その症状は、入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害など多岐にわたるとされています。
「単なる不眠と思っていたら、実はうつ病だった」というケースも少なくありません。
うつ病患者の約80%~85%に不眠が認められ、その症状は、入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害など多岐にわたるとされています。
「単なる不眠と思っていたら、実はうつ病だった」というケースも少なくありません。
薬やアルコールなどに関連した不眠
医薬品や嗜好品などの影響で、睡眠が妨げられるケースです。
睡眠に影響を及ぼす薬剤はさまざまあるため、治療のために飲んでいる薬の成分が原因で不眠を引き起こすことがあります。
また、タバコに含まれるニコチンやコーヒー・紅茶などに含まれるカフェインには覚醒作用があるため、睡眠に悪影響を与える要因の一つです。
その他、過度なアルコールの摂取も、睡眠の質と量を損なう要因に繋がります。
睡眠に影響を及ぼす薬剤はさまざまあるため、治療のために飲んでいる薬の成分が原因で不眠を引き起こすことがあります。
また、タバコに含まれるニコチンやコーヒー・紅茶などに含まれるカフェインには覚醒作用があるため、睡眠に悪影響を与える要因の一つです。
その他、過度なアルコールの摂取も、睡眠の質と量を損なう要因に繋がります。
不眠症を予防するために
不眠症を予防するための対策をいくつか紹介します。
是非、参考にしてみてください。
是非、参考にしてみてください。
朝起きたら太陽光を浴びる
眠りの時刻は体内時計によって決まっているため、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることは不眠症の予防には有効です。
人間の体内時計の周期は24時間より少し長めになっているので、毎日リセットしないと少しずつ生活リズムがずれ、寝る時間が遅くなってきます。朝の光には体内時計をリセットする作用があり、目から入った光を脳が感じることで体内時計が1日を刻みはじめ、夜(約14~16時間後)になると眠くなるように準備を整えてくれます。
翌日仕事や学校が休みでも、毎朝いつもと同じ時刻に起きることが大切です。
人間の体内時計の周期は24時間より少し長めになっているので、毎日リセットしないと少しずつ生活リズムがずれ、寝る時間が遅くなってきます。朝の光には体内時計をリセットする作用があり、目から入った光を脳が感じることで体内時計が1日を刻みはじめ、夜(約14~16時間後)になると眠くなるように準備を整えてくれます。
翌日仕事や学校が休みでも、毎朝いつもと同じ時刻に起きることが大切です。
規則正しい食事を摂る
規則正しい食事も体内時計のリズムを整える働きを持っています。
朝起きて朝食を摂ることで、朝の目覚めを促進します。夜食は食べ過ぎると寝つきが悪くなってしまうので、空腹で眠れない時は、消化の良いものを軽く摂るようにしましょう。
朝起きて朝食を摂ることで、朝の目覚めを促進します。夜食は食べ過ぎると寝つきが悪くなってしまうので、空腹で眠れない時は、消化の良いものを軽く摂るようにしましょう。
適度な運動習慣を心がける
運動習慣のある人は不眠が少ないことが多くの研究により明らかになっています。普段運動習慣がない人は、適度な運動習慣を心がけてみましょう。
運動は不定期に行なうのではなく習慣として継続していくと、寝つきが良くなり深い眠りが得られるようになると言われています。ただし、激しい運動は睡眠を妨げるおそれがあるため、早歩きや軽いランニングなどの有酸素運動がおすすめです。
運動は不定期に行なうのではなく習慣として継続していくと、寝つきが良くなり深い眠りが得られるようになると言われています。ただし、激しい運動は睡眠を妨げるおそれがあるため、早歩きや軽いランニングなどの有酸素運動がおすすめです。
寝る前のリラックスタイムを作る
入浴、ストレッチ、ヨガ、アロマ、音楽、軽めの読書など、さまざまなリラックス方法があります。同じ方法でも人や状況により個人差はあるため、自分に合った方法を見付けて寝る前のリラックスタイムを過ごしましょう。
また、寝る前にスマートフォンやタブレットから発せられるブルーライトを浴びてしまうと体内時計の調節が乱れ、睡眠と覚醒のリズムが崩れてしまいます。就寝前1時間はデジタルデトックスをしましょう。
また、寝る前にスマートフォンやタブレットから発せられるブルーライトを浴びてしまうと体内時計の調節が乱れ、睡眠と覚醒のリズムが崩れてしまいます。就寝前1時間はデジタルデトックスをしましょう。
寝る前の飲酒や刺激物を避ける
前述したように、就寝前の飲酒は睡眠の質も量も損なうため、日頃から習慣にしている方はやめるようにしましょう。アルコールを摂取すると筋肉の緊張が緩んでいびきをかきやすくなるため、睡眠時無呼吸症の原因になることもあります。
また、カフェインやニコチンには、眠りを妨げる作用があります。カフェインには利尿作用もあり、トイレが近くなるので、中途覚醒の原因にもなります。
寝る前の4時間はアルコールやカフェインなどの刺激物は控えましょう。
また、カフェインやニコチンには、眠りを妨げる作用があります。カフェインには利尿作用もあり、トイレが近くなるので、中途覚醒の原因にもなります。
寝る前の4時間はアルコールやカフェインなどの刺激物は控えましょう。
心地良い寝室作りをする
不眠症の予防には、心地良く眠れるための寝室環境を整えることも大切です。
自分の体型や季節などに適した寝具を使用するようにしましょう。
また、寝るときの温度は20℃前後、湿度は40%~70%程度が最適であるとされています。
自分の体型や季節などに適した寝具を使用するようにしましょう。
また、寝るときの温度は20℃前後、湿度は40%~70%程度が最適であるとされています。
このように、不眠症にはさまざまな症状や原因があり、改善するためには正しい知識を身に付けて行動していくことが大切です。
また、睡眠時間はただ長ければいいというわけではなく、最適な睡眠時間は人それぞれ個人差があり、年齢によっても変わります。
十分な睡眠時間が取れていないと感じる人でも、日中に疲労感や眠気を感じることなく元気に活動できているのであれば、治療の必要はないようです。
2月3日の「不眠の日」の機会に、今一度ご自身の睡眠について見直してみましょう!
睡眠や寝具のレンタル・丸洗いなどでお悩みの際はアール城南寝具へご相談下さい!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
東京の布団レンタルのプロ「アール城南寝具」
東京都品川区旗の台3-7-10
TEL:03-3781-4547
FAX:03-3781-8887
電話受付時間 9:00~20:00
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇